
こんにちは、セネきちです!
今回は、ペットを愛する人の全ての望みである「長生き」についてのお話です!
小動物や鳥は繊細な生き物。正しい飼育方法と日々のケアで、寿命を大きく延ばすことができます。この記事では、初心者の方にもわかりやすく、長生きの秘訣を具体的に紹介します。
驚きの長生きエピソードも紹介しているので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね!
1. 正しい飼育環境を整える
まずは、基本中の基本、「正しい飼育環境を整える」ということについて解説しますね。
適当に飼育しても長生きしたよ~?なんて言う人もいますが、近年は飼育用品がたくさん販売されていますし、情報もあります。
「適当に飼育した」なんてなんの自慢にもならないので、しっかり準備を整えてお迎えしましょう。また、今既に飼育しているよ!という方も、もう一度飼育環境の見直しをしてみると良いですよ!
適切な温度と湿度管理

小動物や鳥が健康に過ごすためには、適切な温度と湿度がとても大切。
ハムスターやモルモットなど小動物は全体的に暑さに弱く、インコなどの鳥は急激な温度変化にストレスを感じます。
夏はエアコンや扇風機で涼しくし、冬はヒーターや毛布で暖かく保ちましょう。
湿度も40~60%を目安に管理すると安心です。鳥も小動物も湿度が高いのは苦手なので、湿度計を使って、いつも快適な環境を保つことが長生きの第一歩です。
清潔でストレスの少ないケージ作り

当たり前のことですが、どれだけ良い飼育用品を使って、広いケージで飼育していても、汚れていると、病気の原因になります。
毎日フンや食べ残しを取り除き、週に1回は全体をきれいに掃除しましょう。また、狭すぎたり、騒がしかったりすると、動物はストレスを感じてしまうので、種類ごとに適した広さや高さ、遊び道具を考えて、動きやすく落ち着ける空間を作ってあげましょう。
日当たりや静かさにも注意を

小動物や鳥は、日光を適度に浴びることで健康を保てます。日光浴はビタミンDの生成に役立ち、骨の強化にもつながります。
ただし、直射日光や暑すぎる場所は避けましょう。体温が急に上がってしまったり、飼育用品が熱をもつ、餌や水が傷みやすくなるなどのトラブルが起きます。
レースのカーテン越しに日光が入る場所が理想的で、大きな音や振動があるとストレスの原因になるので、静かで落ち着いた場所にケージを置くようにしましょう。
2. 栄養バランスの取れた食事を与える
飼育環境を整えたら、大事な食事面についても注目してみましょう。
実はペット用として販売されているからといって、全てがペットの体のことを考えて作られたわけではないので、ある程度は飼い主さんが餌について調べる必要があります。
また、人間の生活にはペットが口にしてしまうような危険なものがいっぱいで、食べ物でも与えてはならないものばかり。基本的にはペットにはペットの餌だけを与えるようにしましょう。
種類ごとの理想的なフードとは?
小動物や鳥は、その種類によって、必要な栄養がそれぞれ異なります。
たとえば、ハムスターには専用のペレットが栄養バランスに優れており、ウサギにはチモシー(牧草)を食べ放題にして専用ペレットは副食にする、インコにはシード(種)に加えて野菜やボレー粉などを与えるけど、専用ペレットを食べてくれるならそちらを選ぶ、など。

そして、市販のフードを選ぶときは、無添加で信頼できるメーカーのものを選びましょう。パッケージに書かれた「おいしい!」「栄養満点!」などのワードには騙されないようにしてくださいね!
最後に、与える量も重要です。よく食べるからといって欲しがるだけ与えていると肥満になりますので、きちんとパッケージに書かれた量を守るようにしましょう。
与えてはいけない食べ物に注意

人間が食べるものの中には、小動物や鳥にとって毒になるものがあります。
例えば、ネギ類、チョコレート、カフェイン、アボカドなどは絶対に与えてはいけません。また、脂っこいものや甘いお菓子も体に悪いので注意が必要です。
知らずに与えてしまうと、命にかかわることもあるので、与えないようにしましょう。
また、人間の食べ物以外の野菜や果物、ナッツ類なども、食べていいもの・食べても大丈夫だけど健康にはあまりよくないもの・絶対ダメなものがあります。
飼育本などでしっかり確認しておき、迷ったらやめておくようにしましょう。
水分補給も重要!新鮮な水の管理
小動物や鳥も、私たちと同じように毎日新鮮な水が必要です。
水入れは毎日洗って、新しい水を入れてあげましょう。特に夏場は水が傷みやすいので、こまめなチェックが大切です。ボトルタイプの給水器を使う場合は、詰まりやカビに注意し、定期的に分解して洗うようにしましょう。

ちなみに、浄水器の水や人間用のペットボトルの水、煮沸して冷ました水を与える方がいらっしゃいますが、ペットには普通の水道水かペット用の水が一番安全だと思っておいてください。
軟水、硬水のバランスの問題や、カルキが抜けることで傷みやすくなることがあります。
かなりこまめに水の管理ができる方以外は水道水を使うのが無難です。
3. 毎日の健康チェックとスキンシップ
ここらへんから、ちょっと難易度が上がってきますが、きっとここを読んでくださっている方ならば、ペットとのより深い関わりを、楽しんで実践してもらえるはず。
最初は飼育するだけでいっぱいいっぱいになってしまったり、体調不良を見つけられなかったりするものですが、ペットと日々過ごしていくことでだんだん慣れていきますよ。
見た目や行動から体調を判断するポイント
元気があるかどうかは、見た目や行動からある程度わかります。
・いつもより動きが少ない、
・餌を食べない
・毛がボサボサ
・目に力がない…そんな変化があったら注意が必要です。
毎日観察して、ちょっとした変化に気づけるようにしましょう。普段の元気な状態をよく知っておくことがポイントです。
また、小動物や鳥は弱っていることを隠します。瀕死の状態でもギリギリまで姿勢を保ち、餌を食べるふりをすることだってあるのです。

これは、飼育を始めたばかりだったり、1個体しか知らなかったりする場合は気づくのがとても難しいです。
重い症状になる前の段階で体調不良に気づいてあげられるように、日々観察を怠らないようにしましょう。
抱っこや観察で早期発見につなげる

小さな哺乳類や鳥類は自然界では弱い存在。体を掴まれる、触られるというのは捕獲される時ですから、本能的に怖く、鳥(手のりを除く)と小動物のほとんどは、基本的に抱っこや触れ合いが苦手です。
その本能を尊重して、近づいてこない限りスキンシップをしない。という考えも素晴らしいのですが、実は健康チェックのためには抱っこや鳥の保定ができたほうが良いのです。
優しく抱っこしたときに、観察できることはたくさんあります。
しこりがないか、痩せていないか、けがをしていないか、お尻が汚れていないか、爪が折れていないか、など。
また、体調不良やケガの時に動物病院で治療を受けやすくするためにも、スキンシップは毎日少しずつでもやったほうがよいでしょう。

まずは手からおやつをあげるところから始めて、いきなり体を触らないようにしてね!
定期的に体重測定をしよう
体重の変化は健康状態のバロメーターです。
特に小動物や鳥は体が小さいため、ちょっとした体重の変化でも命にかかわることがあります。
週に1~2回、キッチンスケールなどで体重を量り、記録しておきましょう。増えすぎも減りすぎも病気のサインかもしれません。
また、餌をたくさん食べているのに痩せていくということもあるので、餌の食べた量だけで体型を判断しないようにしましょう。

特に鳥と長毛の小動物は、見ただけでは痩せているかどうかが分かりにくいです。
4. 適度な運動と刺激のある生活を提供する
素晴らしい飼育環境、完璧な餌、適度なスキンシップ。
これだけあればペットの体の健康面は完璧に近いのですが、実は「心の健康」も長生きには重要なポイントです。
遊び場やおもちゃの工夫
ペットだけでなく、人間もそうですが、運動不足や退屈はストレスの原因になります。
ケージの中には、そのペットの種類に合ったトンネルや回し車、小さなブランコなど、登ったりかじったりできるおもちゃを入れてあげましょう。定期的におもちゃを交換することで、新しい刺激にもなります。

初めて与えるおもちゃは、まずはケージの外に置いて、怖がっていないか確認してね!
オカメインコでよくある話ですが、気質が臆病なため、新しいおもちゃをケージに入れるとパニックを起こすことがあります。
まずはケージの外に置いて、少しずつ距離を近づけるなど、ゆっくり慣らしていきましょう。
インコの寿命を縮める?退屈のストレス

インコやオウムなどの鳥はとても頭が良く、単調な生活ではすぐに退屈してしまいます。
ストレスにならない程度の適度な刺激を与えることがメリハリある生活を送るためのコツとなります。
例えばこのようなことをしてあげると良いですよ。
・おしゃべりや芸を覚えさせる
・知育系のおもちゃを与える
・日常の中で声をかける
おもちゃは市販のものでも良いですし、飼い主さんと一緒におやつ探しゲームをするのもおすすめ。
紙の中におやつを隠すところを鳥に見せ、紙を簡単に折り、自分で探させるなど、野生で餌を探す感覚に近い体験をさせると脳への良い刺激になりますよ!
放鳥・散歩の注意点と安全対策
インコの放鳥や、ウサギの部屋んぽ(部屋の中の散歩)はとても良い運動になりますが、安全対策が必要です。窓やドアをしっかり閉める、電気コードや危険なものを片付けるなど、事故を防ぐ工夫をしましょう。また、放し飼いにするときは目を離さないようにし、帰る場所(ケージ)を安心できる場所にしておくことも大切です。
5. 定期的なケアと動物病院でのチェック

最後に、病気の予防と、早期発見に関してです。
お迎えから死ぬまで、一度も体調を崩さないということは普通そうそうあることではありません。
元気なうちに動物病院とのつながりをもっておき、病院に行く練習もできると良いですね。

動物病院慣れしていないと、体調を崩した時に慣れない場所に連れていかれたことで大きなストレスになり、悪化してしまうこともあります。
爪切り・羽の手入れなど家庭でできること
ペットの爪は伸びすぎるとケガや病気の原因になります。
爪が自然に削れる飼育用品もありますが、あまり効果がないので切ってあげなくてはなりません。
個体により異なりますが、月に1~2回程度、爪切りをしてあげるとよいでしょう。慣れないうちは動物病院でやってもらい、やり方を教わるのもおすすめです。また、毛づくろいのサポートや、目や耳の掃除も、慣れてきたら少しずつ取り入れてみましょう。

羽に関しては飼い主さんの考え方によるのですが、もし切るならこまめに伸びていないかのチェックが必要です。
小動物にも健康診断は必要?
犬や猫と同じように、小動物や鳥にも健康診断は大切です。
見た目ではわからない病気が見つかることもありますし、病院に慣れる練習にもなります。3カ月~半年に1回程度、信頼できる動物病院で全身チェックを受けると安心です。
普段のケアとあわせて、早期発見・早期治療につながります。
異常が見られた時の対処法
いつもと違う様子に気づいたら、まずは落ち着いて観察し、無理に触らずに安静にさせましょう。
鳥や小動物は症状が目に見えて分かるようになった時には「様子見」は既に危険なことが多いので、早めに動物病院を受診してください。
病気のサインを見逃さず、すぐに対応することが、命を守ることにつながります。
6. 長生きした子たちの飼育例に学ぶ
さて、ここからは、私がペットショップで働いていた時に実際にお客さんから聞いた「長生き」のエピソード、逆に「早く死んでしまった」エピソードを紹介します。
ただし、先に言っておきますが、決して参考になるような話ではありません。
こういうこともあるんだなー、くらいに軽い気持ちで目を通してもらえれば、と思います。
「このオカメインコ、いつ死ぬんですか!?」
ある日のこと。ペットショップにオカメインコを連れたお客さんが来ました。
なんだか不安げな顔をしてこちらに来て、「あの!オカメインコっていつ死ぬんですか…?このコ、平成元年から飼っているんですけど…」と。

その時既に平成も終わりに近づいていた頃だったと思うので、推定30歳。
確かにオカメインコは30年生きるとは言われているのですが、正直な話、そこまで生きることは滅多にないのです。私も聞いたことが無かったです。
オカメインコって、どれだけ健康に気をつけていても、性格的に非常に臆病でパニックを起こしやすいことから事故で亡くなることが多いのです。
あとはヒナの頃に死んでしまう個体も多いため、平均寿命は15年ほどなんです。
そのお客さん曰く、いつまでたっても死なないから怖くなってきたとのこと(笑)
化け猫ならぬ、化けオカメを飼っている気分だったのでしょう。
私から寿命について簡単に説明して、これだけ生きることは本当に珍しくて、そして素晴らしいことなので、ぜひどんな飼育をしているのか教えてほしい、と尋ねました。
すると返ってきた答えは、「え?適当に育ててました…餌はなんか種とかで。冬?ヒーターは使ったことないです…」
驚き!お客さんの記憶では、知人にもらったとのことだったので、たぶん日本のどこかで保温無しの環境で産まれ育ったオカメインコだったからヒーターなしでもいけたのでしょう。
確かにオカメインコは一日の寒暖差の差が大きいオーストラリアにも棲息するくらいなので、元々は強い鳥です。保温無しのところで産まれ育ったならば、それで全然暮らせてしまうのでしょう。
餌はもう…悪い餌のお手本のようなものを与えていたのですが、結果的に長生きしているので、私からは何もアドバイスしませんでした。今さら飼育方法を変えるのは良くないですからね。
この長生きにつながった要因としては以下のようなことが考えられます。
・産まれた環境そのままで育ったこと
※ペットショップからの購入だと、ブリーダー→問屋→ペットショップという流れになることが多く、あらゆる面でストレスが多い
・大好きな種子の餌を思う存分食べていたこと
※本来は脂肪分が多く栄養が偏るので種子食(シード)のみにするのは推奨されませんが、種子食の最大のメリットは、「食のストレスがないこと」。人間も好きなものを食べていたほうが人生楽しいですもんね…
なんというか、「自由」だったんでしょうね。
でもこれはこのオカメインコの強靭な体が長生きの鍵だった気はします。種子だけ食べていても太りすぎることなく、病気にもならなかったわけですから。
結局、その長生きオカメインコの飼い主さんは、「まだ生きるのかぁ」とつぶやきながら帰っていきました。私が見た時点でもまだ健康そうだったので、しばらくは生きていたと思います。
いろんな条件が重なって、長生きオカメインコになったわけですが、もうちょっと喜んでほしいなとは思いましたね!
なんだかいつも早くペットが死んでしまう人の話

今度はオカメインコの話と真逆の話になります。
Aさんは、ウサギやハムスター、文鳥など、小動物も鳥も何度も飼ったことがあります。
餌は厳選し、高価なペレットを中心に与え、適度におやつも。病院への定期検診に日々のふれあいでは体調のチェックを決して欠かさない、しっかり者の飼い主さんです。
だけど、ペットたちはあまり長生きせず、ウサギは5~6年、ハムスターは1年半くらい、文鳥も6年くらい。ちょっと早めです。
いったいなぜでしょうか。私はAさんには言えなかったのですが、思い当たる節はありました。
おそらく、ですが。
Aさんは、ペットたちの体調が気になるあまり、ベビーの頃から頻繁に体を触り、病院にもよく連れて行っていたのですが、飼育していたコたちがたまたまストレスを感じやすい性格ばかりで、体を触られたり、病院に行くたびに多大なストレスを感じていたのでは、と。
病院に行ったり日々の健康チェックはもちろん大事ですが、じっくり時間をかけて慣らすか、頻度を減らしたほうが良かったのかもしれませんね。
Aさんの飼い方は決して悪くない、でもそれぞれの個の性質を考えて、もう少しおおらかに飼育してあげると良かったのかもしれません。
寿命を全うする幸せなハムスター
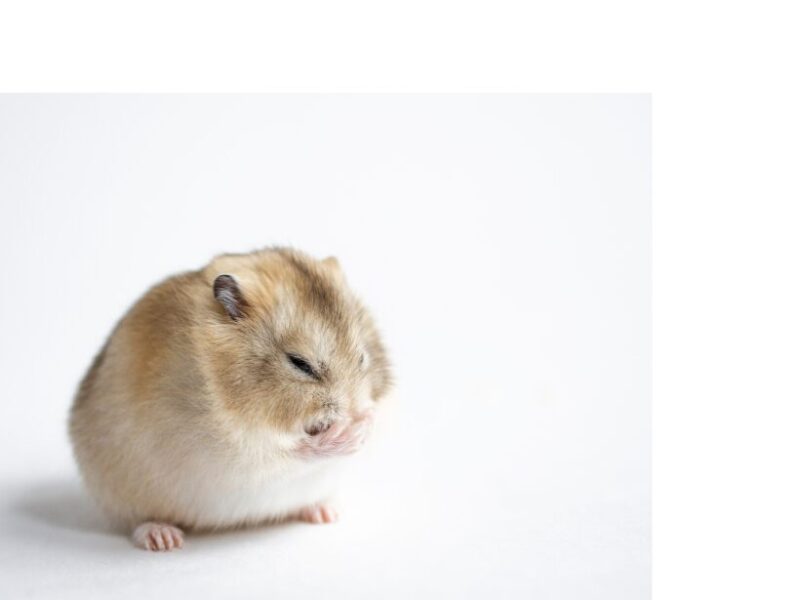
最後の話です。
私がペットショップで商品の品出しをしていた時に、ハムスター用品売り場でうずくまって泣いている女性を発見しました。
どうしたんだろう!と思い、話を聞いてみることに。
その女性は大泣きしながら「ジャンガリアンハムスターを飼っているんですけど、もう死んでしまうんです。もう2歳8か月なんです、毛もぼさぼさで、よたよたしています。嫌だ嫌だ、お別れしたくない、死んでほしくない!!」と言いました。
ジャンガリアンハムスターが2歳8か月となると長生きしているほうです。なかなかそこまではいきません。その女性の泣き方からも、どれだけ大事にしていたかが分かります。
でも、「きっと大丈夫です」なんて言えない、だって間違いなく寿命が近づいているから。
なんと声をかけたかは覚えていません。
でも、素晴らしい飼い方をしたであろう飼い主さんの日々を称え、そしてハムスターは大往生を迎えるだろうから、せめて人生の最後にはおいしいものをいっぱい食べてもらいましょうと、好物を聞いたうえで老ハムスターでも食べられるおやつを一緒に選んだ記憶があります。
本当なら、全てのペットがこんな人生を送れるのが理想ですよね。
まとめ
さて、ここまでいろいろ解説してはきたものの、結局私たちにできるのは「最大限ペットの幸せを考えてやること」です。
そして、飼育本やネットの情報も大事だけど、一番大事なのは「自分が飼っているコの性質をよく理解すること」です。
何が一番好きなのか、何が嫌なのか、これをできるだけ早く把握しましょう。
時に飼育のセオリーから大きく外れた性質をもつ個体もいるということを受け入れましょう。
ペットを飼うということは、その命を預かるということです。かわいいだけでなく、毎日の世話や健康管理など、やるべきことがたくさんあります。
しっかりと責任を持ってお世話することで、動物たちも安心して暮らすことができます。命の重さを忘れずに向き合いましょう。
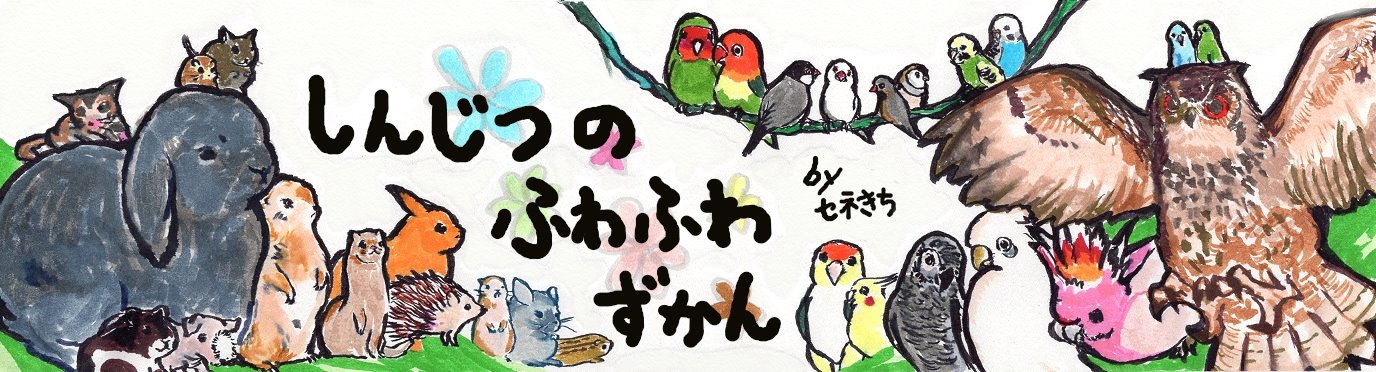





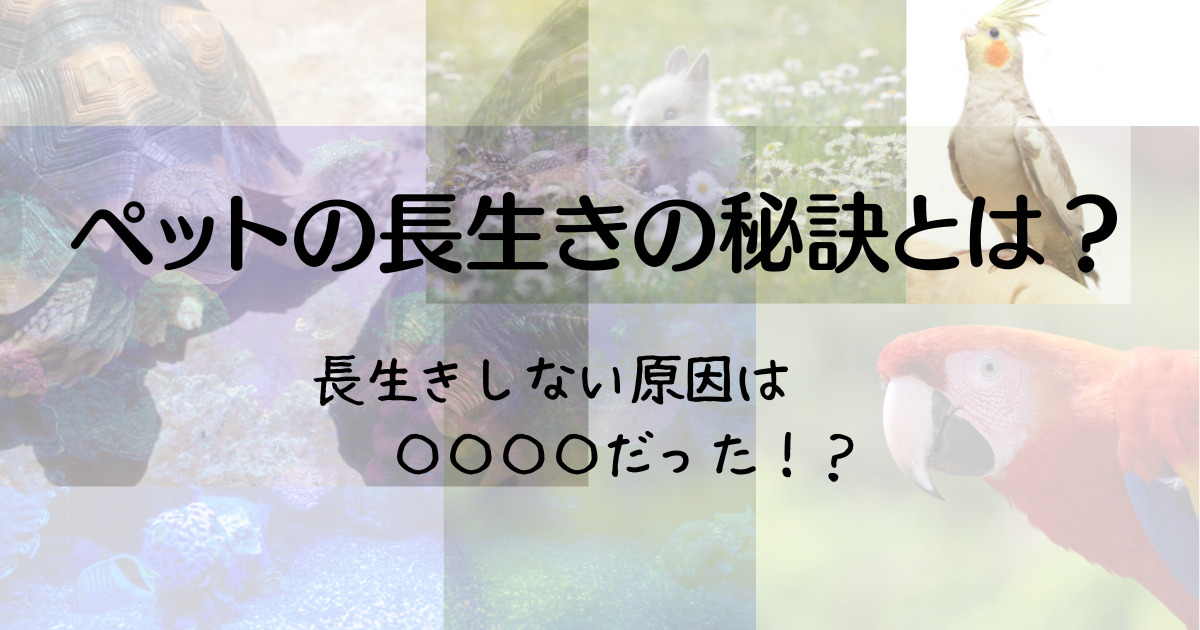


コメント