ウサギ好きのみなさん、こんにちは。セネきちです!
今回はウサギについてのお話ですよ。

みなさんは“うさんぽ”という言葉を知っていますか?
“うさんぽ”とはうさぎ+お散歩、からできた、造語です。
ウサギと“うさんぽ”・・・なんだか楽しそうですよね。

でも実際は、ウサギを、外で“うさんぽ”させている人、滅多に見ないですよね。

実は“うさんぽ”はメリット、デメリットをしっかり知っておかないと思わぬトラブルになることもあることから、賛否両論があるのです。
もし、あなたがウサギを飼ったばかりで、お散歩に行こうとしているならば。
一度今回の記事を読んでからにしてください。
うさんぽってどこでやるの?
自宅の庭なら放しておくことはできる?
うさんぽさせようと思ったけどハーネスを付けると暴れる・・・!
うさんぽに関する色々な意見も踏まえながら、トラブルにならないためのやり方をみていきましょう!
そもそも、うさんぽとは?

うさんぽとは先ほど冒頭でもお話したとおり、正式な言葉ではありません。
ウサギを外に出してお散歩させるという意味の造語です。
お散歩させるといっても、犬のように、リードに繋いで飼い主さんの横を歩くという感じではありません。
庭や公園などの広くて安全な場所にキャリーケースに入れて連れて行き、飼い主さんが見ている場所で自由に動き回らせることをいいます。

一見楽しそうに見える“うさんぽ”ですが、冒頭でお話したとおり、賛否両論あるのはなぜなのか、メリット、デメリットをみていきましょう。
うさんぽのメリット
まずは“うさんぽ”のメリットからみていきましょう。
メリット①日光浴ができる

日光浴ができないから早く死ぬ、とか病気になる、とかではありませんが、太陽の光というのは適度にあたることで体に良い影響を与えます。
例えば、日光浴をすると、体内でビタミンDが生成され、カルシウムの吸収を良くしてくれます。
また、紫外線を浴びることで、殺菌効果も期待できます。
全くやらないよりは断然、健康の維持に役立つでしょう。
メリット②ストレス発散になる

広い場所で暖かな日差しに包まれて走り回るというのは部屋の中ではなかなか難しいもの。
自由に動き回ればストレス発散になりますね。
メリット③外の世界に慣らすことができる
ウサギを飼育していると、急に体調を崩したり、ケガをして病院に連れて行かねばならないことがあります。
そんな時、部屋の中しか知らないウサギの場合、キャリーに入れられること、移動、そして全く知らない外の世界に出るだけで大変なストレスを感じます。
治療を受ける前にすっかり弱ってしまうことも。
その点、うさんぽに慣れているウサギならば、それらの行動がストレスになることなく、病院に行き、治療を受けることができる、というわけです。
その他にも地震などで外に一時的に出さなければならなくなった時にも、うさんぽに慣れているコのほうがストレスを感じにくいでしょう。
メリット④飼い主さんが楽しい

これはおまけみたいなものですが・・・
“うさんぽ”はぴょんぴょん跳ねる姿を見ることができますし、ハーネスを付けた姿もかわいいものです。
飼い主さんにとって、とても素敵な時間になるでしょう。

メリットはこのような感じです。
ウサギがウサギらしくのびのびと生活できて、万が一外に出さなくてはならなくなった時の練習にもなるというのが大きなメリットです。
うさんぽのデメリット
ここからはデメリットです。
“うさんぽ”のデメリットは、どれもウサギの命にかかわるものばかりなので、先に知っておいてほしいことばかりですよ!
デメリット①ウサギの性質に向いていない
ウサギというのはもともと巣穴を持ち、敵から逃げる側の動物です。
トイレを覚えるのも、あちこちに排泄すると敵に場所がバレるために決まった場所でする、という性質が残っているためです。
外の世界は自分の臭いはなく、敵も多いです。
ウサギにとって見知らぬ場所は基本的に「怖い」場所。
なので「散歩」という行動自体がウサギの飼育に合っていないという意見があります。

これをいっちゃあおしまい!なんですが、事実なんですよね。
デメリット②“うさんぽ”する場所があまり無い
“うさんぽ”はとても魅力的ですが、実はそもそもウサギを放てるような場所を見つけるのが困難なのが実情です。
安全性に欠ける場所ではあらゆる危険が待っています。

ちなみに最適な場所とはこのような場所です。
・家から近い場所
移動時間が長いと、ウサギのストレスになります。
歩きでも車でも、5~10分で着く場所が理想です。
・農薬のまかれていない場所
ウサギは草を食べます。農薬は少量でも口に入ると危険です。
・花壇が少ない場所
花壇に植えられている花は有毒なものが多いためです。
・犬の散歩コースではない場所
犬はウサギにとっては捕食者です。臭いだけでも怖がる場合があります。
・子供が集まらない場所
“うさんぽ”最大の敵かもしれません・・・!
ウサギが散歩していれば間違いなく子供が寄ってきます。
子供が悪いわけではありませんが、本当に予想の付かない行動をとるので、子供が多い場所はウサギの散歩には向きません。
・川、道路が側に無い公園
“うさんぽ”中にウサギが何かの拍子に走ってしまい、リードから離れたり、ベストが脱げてしまうことがあります。
川や道路が近くにあり、柵もなければ、命に関わりますし、排気ガスも気になります。
一番の理想は、自宅に広い庭があることです。
もちろん農薬や有毒な植物の無い庭です。

これだけの条件が全て揃うことがまず難しいため、“うさんぽ”が実現できないのです
デメリット③ハーネスを付けるのが難しい
“うさんぽ”にはハーネスやリードを付けていきますが、まずこれらを付けることが難しいです。
ウサギは体を固定されることを怖がる動物です。
敵に捕食される時の状況と同じですから。
抱っこが苦手なコも多いので、そもそも付けるために固定することもできず、断念する人も多いです。

ハーネスや首輪をすんなり付けることができるのは犬や一部の猫くらいなのです。
デメリット④誤食の危険性
ウサギは草を食べますが、それ以外のものも外にはたくさんあります。
有害な植物、農薬のかかった植物は飼い主さんがある程度見分けて場所を選ぶこともできますが、犬のフン、たばこ、ゴミ・・・ 他には何が落ちているか分かりません。
誤食してもすぐには症状が出ない場合もあるため、“うさんぽ”中は始終目を離さず見ている必要があります。

始終張りついてウサギの口元を見ているのは大変…
デメリット⑤癖になることがある
基本的にウサギはお散歩に向かない、と書きましたが、中には“うさんぽ”が大好きなコもいます。
そういうコは問題なく外に出すことができるわけですが…
逆に今度は出してもらえないことにストレスを感じるようになり、ケージをかじって出せアピールをするようになるコがいます。
冬や真夏はうさんぽさせるのは難しいので、我慢してもらうことになりますが、自由に動けることを知ってしまったウサギにとっては出してもらえないことはストレスになることも。
もし、飼育しているコが外に出たくて、窓に寄っていって、アピールしたとしても、出せない時は出してはいけません。
アピールすれば出してもらえる、と覚えてしまいます。

メリット、デメリットはこんな感じです。
さて、ここまででお分かりかと思うのですが、“うさんぽ”はメリットよりもデメリットのほうが大きいんですよね。
これが賛否両論分かれる理由というわけです。
メリットは魅力だけど、安全な“うさんぽ”ができる場所が無い・・・
デメリットを克服する自信が無い・・・
家の中で安全に飼っていたい、ベランダで日光浴させるくらいでいい
と感じ、“うさんぽ”を断念した人もいるでしょう。
その判断は間違っていません。

室内でもウサギにとって幸せな環境をつくることはできますからね。
まとめ
今回は、“うさんぽ”について考える、ということで、メリット、デメリット、を説明させていただきました。
ウサギ飼いなら一度は憧れる“うさんぽ”
正直、実行がなかなか難しいものです。
飼い主さんが“うさんぽ”に憧れていても、どうしてもハーネスや外の世界に慣らすことのできないウサギはいます。
もし自分の飼っているコがそういうタイプのコなら、無理に“うさんぽ”練習させず、時々窓を開けて、日光に触れさせてあげるくらいにしましょう。

飼い主さんとウサギにとって、ストレスのないように飼育ライフを楽しんでくださいね
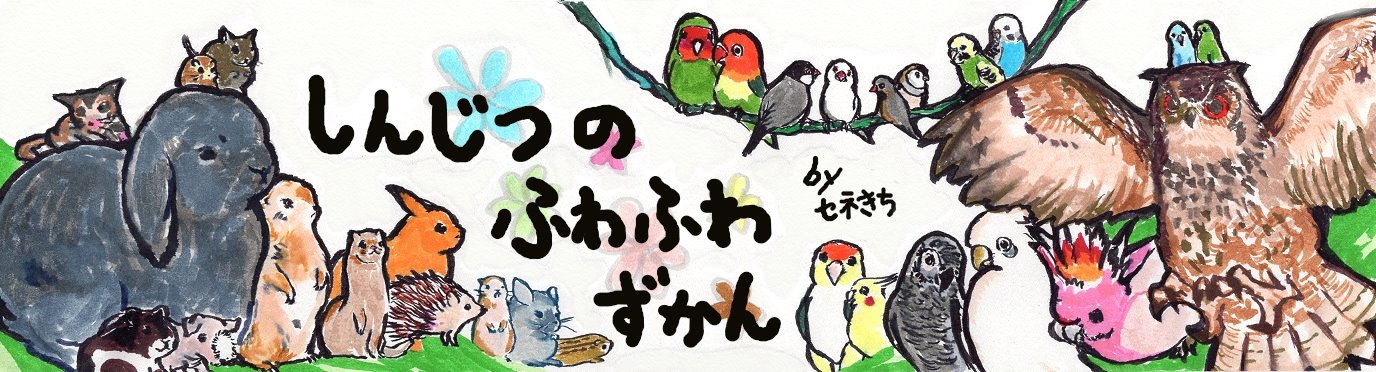





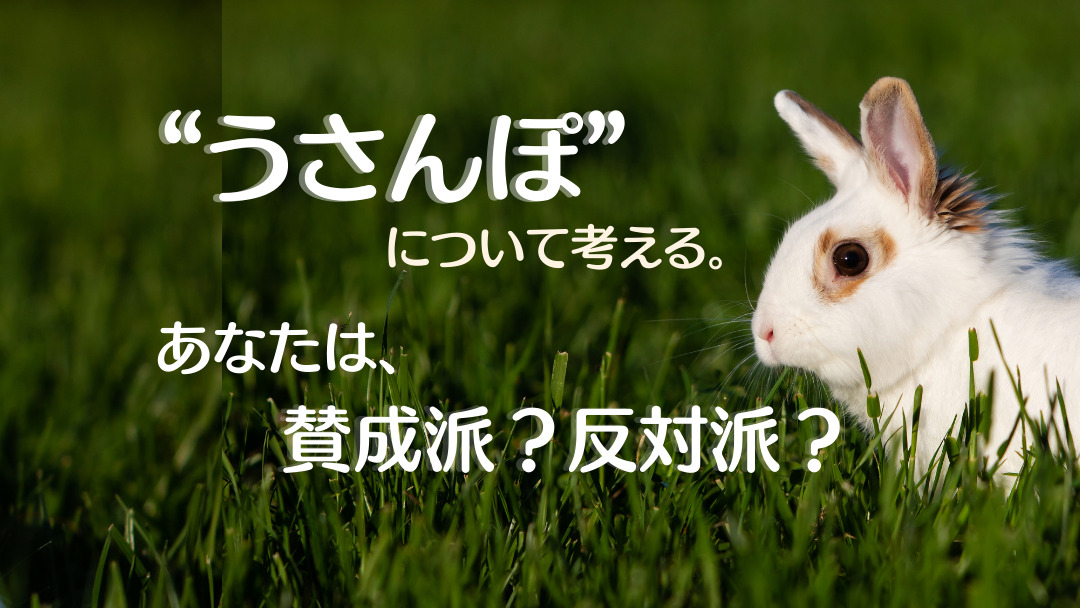


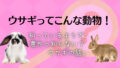

コメント